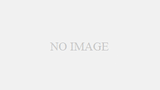CPI Tokyo 2025(国際指揮プログラム2025東京)1日目のメモです。
8カ国12人の参加者!まずは自己紹介。名門音楽大学の学生、指揮者、教育者、作曲家などさまざま。今日初めて会ったと思えないほどすぐに親しくなる。ベートーヴェンのピアノソナタ「悲愴」第2楽章のコンピューター演奏とピアニスト演奏を聴き比べて何が違うか考える。そして音楽の現象学へ。
音はエネルギー。音はエネルギーを放出して沈黙に帰っていく。音が鳴り続けていると言うことは沈黙に抵抗しているということ。失われた分だけエネルギーを加えると振り子が揺れ続けるように音は鳴り続ける。音のクリエーションとリリース。大きい音、高い音、混んでいる音はリリースに時間がかかる。
曲のエネルギー構造を捉える。グルーピングを探し、音量の構造を探し、クライマックスを探す。和声理論は関連しているけど、頭で考えるのはやめて、感覚的に捉える。指揮台に立つ指揮者のすることは、Make beautiful music、Free the mind、Free the body、Be the music。
ピアノで2つの音を聞き、そのあとの音を歌う実験。演奏者は音を聞き、この先の音程、音量、持続時間を予測して合わせられるけど、visual confirmationが必要。そこが指揮者が演奏者を助けられるところ。
後半はずっとムーブメントの実習。不必要な筋肉の緊張を取る。ダウンビートを振りながら、野球選手がフォームの細かなチェックをするように、肘の上下・左右・前後の位置をチェックし、力が入っていないかをチェックする。肩と肘の関節が無駄なく連動して動くようにする。
その後、ダウンビートの1:2のレガートと、1:3のスタッカートの振り分け。アラ・ブレーヴェ(2拍子)、トライアングル(3拍子)、クロス(4拍子)のパターンの振り方。上昇と下降でスピードが同じになるようにコントロール。これまで習ってきた指揮のムーブメントと共通のこともあるし違うこともある。
違う型を入れてアンラーン。無意識的になっている動きを意識化できて有意義。変えたいと思っていた動きを変えるヒントが得られそう。宿題はエネルギー構造をこれまで小さく把握したのを今度は大きな括りで捉えていく。同じモーツァルト「ディベルティメント」K.136第2楽章を使って。腕はすでに筋肉痛💪