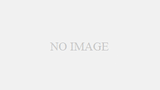CPI Tokyo 2025(国際指揮プログラム2025東京)3日目のメモです。
今日からオーケストラの指揮!午前中は各パートのトップ4人のみなさんに指揮。午後にマーカンド先生とディスカッションして、夜は弦楽オーケストラの指揮。15人のオーケストラのみなさんはとてもフレンドリーで、10人の指揮者×15分のハードワークにもかかわらず、辛抱強く演奏してくださる。
今日の課題曲はモーツァルト「ディベルティメント」K.138かエルガー「弦楽セレナード」。私はエルガー「弦楽セレナード」第1楽章を選択。指揮台で音楽を楽しませてもらうことができたけど、指揮はあまりうまくいかなかった。技術的なこと音楽的なことがなかなかマッチしない。
技術的な課題を意識して振ると固くなって音楽的でなくなるし、自由に音楽的に振るとこれまで習ってきた技術と関係ない振り方になってしまう。暗譜で振らなければいけないのがさらに事を悪くして、振り間違えもしてパニクってしまう。打点の高さでシェイプを見せるのはなんとかかろうじて。
他の参加者の指揮と、それに対してマーカンド先生がどういう指導をするのかを見られるのはありがたい。発見がいろいろ。「振り付け」を考えてくる作戦はうまくいかない。キューはもちろんアイコンタクトすらもしばしば演奏者の邪魔になる。各パートに指揮で細かく指示するのはほとんどいらない。
振り付け、アイコンタクト、各パートへの指示は音楽に対して局所的、短期的に反応してしまい、それ以外の音が聞けなくなるし、音楽の流れを切ってしまう。演奏者もびっくりして指揮を見なければと思い、他の演奏者とのつながりが切れてしまう。体を動かしすぎたり力が入ったりすると音が聞けなくなる。
指揮者はまず音をよく聞き音楽に入れてもらう。音楽とつながってから仕事が始まる。音楽とつながっていない状態での動きはほぼ無意味。指揮者の大きな仕事は演奏者と音楽をつないで一つにすること。指揮者が「音楽になる」ことはその助けとなる。音楽について指示することは時にその邪魔になる。