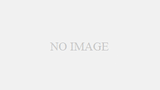CPI Tokyo 2025(国際指揮プログラム2025東京)2日目のメモです。
Q&Aから。音楽はドミナントトニックを使って転調を繰り返しながらエネルギーを生成していく。参加者とマーカンド先生がシューマンでは、ベートーヴェンの交響曲ではと議論し、曲が頭に入っている先生はすぐにピアノで弾いて示す。すごすぎてついていけない。。。
テンポについて、正しいテンポはないけど、間違ったテンポはある。音楽には情報量がある。その情報量を聴き手が処理できないのは速すぎる。逆に前後の音のつながりを見出せなくなるのは遅すぎる。だから演奏会場によってテンポは変わる。自転車に乗っている時には車の半分の速度でも速く感じる。
マーカンド先生がオーケストラに言わないこと。I want:演奏者は私のために働いているのではない。Thank you:私は演奏者のために働いているのではない。演奏者も指揮者もみんなのために働いている。Watch me:代わりにlisten、connectと言う。
ムーブメント実習は1:2のレガートと、1:6のスタッカーティシモ。1:6の場合は拍の1/6の長さで上昇し、4/6の長さは上にいて、1/6の長さで下降するということ。上昇と下降が同じ長さになるように。とても合理的なトレーニング法。
予備拍。振り始めのインパルスを力を入れずスッと始められるように。小節の途中から始まる時には高い位置からの下降で始める。予備拍で息を吸わない。私も含めて習慣になっている人は直すのに苦労している😅。
モーツァルト「ディベルティメント」の136と138を使って、ハーモニー構造とクライマックスの関連について確認。クライマックスがわかれば、音量とリズム強度という2つの道具を使ってシェイプを作ることができる。
そしてシェイプと指揮をコネクトすることについて。打点を上げたり下げたりすることでシェイプを見せることができる。そして課題曲のドヴォルザークの出だしの振り方を指揮以外の人はみんなで歌って練習。合唱楽しい。
2と3を組み合わせた複合拍子。こういうふうに振り方を練習すればいいのかぁ。これでアルメニアンダンスの振り方を教えることができる。
演奏者とコネクトすること。演奏者を信頼すること。音楽になること。一体になれば、何かをしようとしなくても、自然に影響を与えられるようになる。コネクトが音楽の醍醐味かもしれない。
マーカンド先生の熱意はすごい。丁寧かつ合理的で、求める水準の高さから時に厳しさも感じる。私はとにかく力が入るので力を抜くことを言われる。肘の位置も変わったので、アンブシュアを変えた感じで、常に気をつけていないといけない。後半は「Free」と言われることが多くなってきた。ただ自由に。
朝から夜までで、疲れが見える参加者もいる。私は東京開催でホームなので、自宅から通えるし、時差もないけど、みんなは高い飛行機代を払い、苦労もしながら一生懸命学んでいる。私は英語力や音楽知識のなさで苦労をしながらもついていっている。がんばっている仲間たちと一体感が生まれてくる。
これをスタバで打っていると、マーカンド先生がやってきた。エレベーターで聞こえる「ドアが閉まります」「ドアが開きます」の日本語の発音の練習。
いよいよオーケストラの指揮!