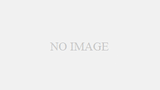CPI Tokyo 2025(国際指揮プログラム2025東京)4日目のメモです。
午後はビデオレビュー。一人一人の参加者がマーカンド先生と前日の指揮の映像を見ながら、課題を明確にしていく。自分の学生にもいつも言うことだけど、自分が指揮をしている映像を見ることが、一番改善につながる。自分が振っている様子は見ていて気持ちのいいものではないけど。
自分でやっていたと思っていても全然動いていない。自分がやっていないと思っても変な動きをしている。ビデオのフィードバックは率直で嘘がない。ビートをはっきり振れていないところで、でも演奏はぴったり合っていて、先生はなぜだかわからないと言っていたけど、私は「ホームだから」と答える😅。
夕方にQ&A。絵を見る経験と、音楽を聴く経験は似ているところがある。絵を近くで見すぎると描かれている物同士のつながりが失われる。離れて見すぎると何が描かれているかわからない。適切な距離で見れば、絵は一つの経験となり、絵と自分の境目がなくなる。物理的な時間と空間を超越した経験となる。
音楽も、細かく局所的に反応しすぎると、バラバラなことが突発的に起こるだけでつながらない。大雑把に捉えすぎてもつながりが見えない。「今」は過去や未来とわずかにつながっている。それらがまとまりとなって一つの経験となっている。演奏はエネルギーを制御してそのまとまりをつくること。
(絵の話は、メルロ=ポンティの『知覚の現象学』で、セザンヌの「サント=ヴィクトワール山」を例にして出てきた気がする。一つの経験の話は、デューイの本で出てきた気がする。)
夜はマーカンド先生のチェリビダッケについてのレクチャー。急遽、通訳をすることになり、でもそのおかげで事前に台本を読ませてもらえ、きっちり理解できてありがたかった。今回、チェリビダッケ=マーカンド先生のエネルギー構造の理論、音楽の現象学を体験的に学べたことは財産。音楽が変わる。
そして、この構造を、コーポロン先生はアーティキュレーションとパート間の音量バランスという道具を使って実現しているということも理解できた。