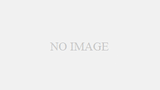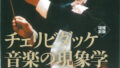CPI Tokyo 2025(国際指揮プログラム2025東京)の振り返りです。
ボルチモア室内管弦楽団音楽監督でニューヨーク・フィルハーモックなどさまざまなオーケストラを指揮してきたマーカンド・ザーカー先生は指揮者の仕事を次の4つに整理する。美しい音楽をつくる、心を自由にする、体を自由にする、音楽になる。
美しい音楽をつくる(Making beautiful music):そのために必要なのはエネルギーの構造をとらえること。音たちはエネルギーの生成と解放を通してつながり、一つのまとまりとなる。それを聴く人に一つの経験をもたらす。
作曲家は音程、音量、リズムの密度、和音、和声構造という道具を使ってエネルギーの構造を示してくれている。クレッシェンド、ディミヌエンド、アッチェルランド、リタルダンド、フェルマータ、足された小節、スフォルツァンドはすべてエネルギーの生成と解放に関わっている。
音は大きくなり、高くなり、重なるとエネルギーが大きくなる。エネルギーが大きくなれば解放するのに時間がかかる。演奏者がエネルギーの生成と解放のために使える道具は音量とスピード。増大すれば生成、減少すれば解放。加速すれば生成、減速すれば解放。
よく響く場所では、反響によって音が多くなるので、解放に時間がかかる。だから音量を抑えるか、テンポをゆっくりにする必要がある。逆に響かない場所では、すぐ解放されて音同士が切れてしまうので、音量を上げるか、テンポを早くする必要がある。
和声もエネルギーの生成と解放をサポート。調を変えながらドミナントトニックを繰り返して生成し、最後の基調でのドミナントトニックで解放する。でも、頭で理論的に和声構造を考えすぎるとかえって見失う。感覚を大事に。
曲を勉強する際には、インパルスから始まるグルーピングをつかみ、生成と解放の分水嶺であるクライマックスを探す。グルーピング内でのエネルギーの増減を捉える小さなレベルと、グルーピングのつながりの中でのエネルギーの増減を捉える大きなレベルで把握する。シェイプが見えるようになる。
エネルギーの構造を捉えておらず、変なところで小さくなったり、ゆっくりになったりして、迷走する演奏がよくある。エネルギーの構造に音量とスピードを沿わせれば、自然でオーガニックな演奏になり、究極的には物理的な時間と空間の世界から自由になる超越をもたらす。
心を自由にする(Free the mind):聴くこと。音に意識の全てを向け、すべての音を聴く。考えすぎない。チェリビダッケは仏教に強い関心を持っていたけど、マインドフルネスに似ている。
キューやアイコンタクトをしようとすると、ひとつのパートに意識が向いてしまい、他の音は聞こえなくなる。キューやアイコンタクトは演奏者に「何か悪いことをしたかな」「何かを直さないといけないかな」と思わせてしまう。
体を自由にする(Free the body):不必要な力を取り除く。首、肩、腕が緊張しないように。緊張すると聴けなくなる。指揮者の体の緊張は、演奏者の体の緊張につながり、音が固くなり溶け合わなくなる。体に力が入ると指揮が音楽から離れ、音が一つにならなくなる。他の指揮者の演奏を聴いて実感した。
緊張は不自然で余計なジェスチャーを生み出し、演奏者を驚かせてしまい、緊張を生み出す。演奏者はそのジェスチャーに反応しなければならないから、音から離れてしまう。肘が上がると肩に力が入る。肘を落とし、肩、肘、手首が一直線になるようにする。すべての関節を連動させ、腕全体を動かす。
すべてのビートはダウンビート。打点で沈む時間、上で浮遊する時間の長さを変えることでスタッカートにしたり、レガートにしたりできる。上昇の時間の長さと下降の時間の長さを同じにするとパルスと演奏を合わせられる。
エネルギーの高さは、力で見せるのでなく、打点の高さで見せる。フォルテやクライマックスでぐっと力を入れず逆にリラックスする。また、予備拍で息は吸わない。息を吸うと演奏者の体に緊張が走ってしまう。
音になる(Be the music):音をよく聴き、音に入れてもらう。音とつながり、演奏者とつながる。つながってはじめて影響を与えられる。つながっていない状態でのジェスチャーは無意味。指揮者の体はエネルギー構造に沿ったシェイプになる。演奏者は見えるシェイプから確信を持てる。音が一つになる。
今回、一番大きな学びとなったのは、マーカンド先生、そしてその師匠のチェリビダッケの理論の核心であるエネルギー構造のこと。これがわかるようになり、これに体を合わせることができれば音楽が変わる。
エネルギー構造については今までもなんとなく感じていたけど、理論と言葉を得て明確化された。またエネルギーの解放を近視眼的に捉えていた。大きなエネルギーは1音では解放されない。少しずつ生成していくように、クライマックスからゆっくりシェイプをつくりながら解放していく。
また十分にエネルギーを生成させなかったり、テンポが遅すぎたりすると、エネルギーが枯渇してしまい、音が推進できなくなって死んでしまう。
体については緊張という長年の課題とまた向き合う。打点の高さでエネルギーの高低を見せるのは新発見。ビデオで確認し、かなり有効だと思った。吹奏楽でどれぐらいできるかわからないけど、曲によってはとても有効だと思う。来学期の吹奏楽ゼミは生かせそうな曲がいくつかあるので、ぜひ試してみたい。
演奏者に指示を出すのでなく、音楽になることによってもたらされる効果も実感した。演奏者をおどかさない。演奏者が聴き合うことの邪魔をしない。演奏者をより信頼することにもつながる。
はじめて弦楽オーケストラを指揮して、弦楽器のことを知り、さらに興味を持った。弦楽器が得意な消えるような終わり方ははじめての経験!
そしてどのように指揮を教えるかということもマーカンド先生のそばで見させてもらって学ぶことができた。課題の異なる10人の指揮者に対して、先生はさまざまな引き出しで、真剣に、辛抱強く向き合い、変化させようとしていた。
また弦楽オーケストラを指揮できる機会があったらうれしいなぁ。ドヴォルザークの弦楽セレナードと管楽セレナードをやるコンサートとかできたら素敵。管楽器も入ったオーケストラもまた指揮できたらうれしい!